【Synth1講座:第一回】無料シンセSynth1の「顔」を知る!UIと音作りの基本フロー徹底解説
DTMを始めたばかりの方から、もう一歩踏み込んだ音作りをしたい方まで、世界中で愛用されている伝説的なソフトシンセをご存知でしょうか? それが、日本の開発者、戸田一郎氏がフリーで提供している「Synth1」です。
「無料のシンセなんて、どうせ機能が限られているんでしょ?」と思われがちですが、Synth1はそんな常識を覆します。その圧倒的なCPU負荷の低さと、有料プラグインにも引けを取らないクリアでパワフルなサウンドは、まさに「プロ仕様」。多くの著名なクリエイターも、楽曲制作の場でこっそり愛用していると言われています。
今回は、あなたが手元にSynth1の画面(バージョン V1.13 64bit beta2 2014.7のUI画像)を置きながら読み進められるよう、Synth1の「顔」であるユーザーインターフェース(UI)の全体像と、音が生み出される基本的な流れを、どこよりも分かりやすく徹底解説します。これを知れば、Synth1を使いこなすための第一歩は完璧です!
なぜSynth1は「無料」なのにDTMユーザーの「定番」なのか?
- 「Nord Lead」直系の、クリアで力強いサウンド:
Synth1は、スウェーデンのClavia社が開発した伝説的なアナログモデリングシンセ「Nord Lead」シリーズに強くインスパイアされています。このDNAを受け継いでいるため、無料とは思えないほどの芯が太く、抜けの良い、存在感のあるサウンドが特徴です。特に、楽曲の骨格となるベースライン、空間を彩るパッドサウンド、メロディを奏でるリードシンセなどでその真価を発揮し、ミックスの中でも埋もれることなく、聴き手にしっかりと届きます。 - 驚異的な「軽さ」と抜群の安定動作:
最新のDAW(デジタル・オーディオ・ワークステーション)環境でも、Synth1は非常にCPUへの負荷が低いことで知られています。これは、あなたのPCに優しいだけでなく、同じ楽曲内で何トラックもSynth1を立ち上げても、パフォーマンスの低下や音切れ、フリーズといったトラブルが起こりにくいことを意味します。特に古いPCやスペックに不安のあるノートPCでDTMをする方にとっては、まさに救世主のような存在です。 - 無駄を排した、直感的で分かりやすいインターフェース:
Synth1のGUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェース)は、余計な装飾がなく、非常にシンプルです。しかし、このシンプルさこそが、音作りの本質を学ぶ上で非常に優れています。シンセサイザーで音が生み出される基本的な信号の流れ(音源→音色加工→音量変化→エフェクト)に沿ってパラメーターが配置されているため、初心者でも迷うことなく、各ノブやスライダーが「何をするものなのか」を直感的に理解できます。まるで、目の前にアナログシンセの実機があるかのような感覚で操作できるでしょう。 - 世界中のユーザーが共有する、膨大な「無料プリセット」:
Synth1のユーザーは世界中にいます。その膨大なコミュニティによって、数えきれないほどの高品質な無料プリセット(音色データ) がインターネット上で公開されています。数千、数万といったプリセットバンクが無料で配布されており、ダウンロードしてSynth1に読み込むだけで、すぐにプロクオリティのサウンドを試すことができます。自分で音作りをするのが苦手な方でも、すぐに楽曲制作に活用できるのはSynth1ならではの大きな魅力です。
Synth1のUI全体像を把握する:パネル上の「区画」を理解する
Synth1のUIは、一般的なアナログシンセの内部構造を視覚的に表現しています。パネルを上から見ていくと、いくつかの大きな「区画(セクション)」に分かれていることが分かります。

- 左側全体(Oscillators & LFO):
- 一番上にあるのがOscillators(オシレーター) セクションです。ここが「音の元となる波形」を作り出す心臓部。
- その下にあるのがLFO(ロー・フリークエンシー・オシレーター) セクション。音に周期的な「揺らぎ」や「動き」を与えるためのコントローラーがここに集中しています。
- 中央上部(Amplifier & Filter):
- 左寄りにFilter(フィルター) セクション。オシレーターで作られた音の「明るさ」や「キャラクター」を調整する部分です。
- 右寄りにAmplifier(アンプ) セクション。音の「時間的な変化(立ち上がり、減衰、持続、余韻)」を制御する重要なセクションです。
- 右側全体(Effect & Voice):
- 一番上にあるのがEffect(エフェクト) セクション。音に「空間的な広がり」や「特殊な質感」を与えるための内蔵エフェクター群です。
- その下にあるのがVoice(ボイス) セクション。同時発音数やユニゾン(音の重ね)といった、シンセ全体の「発音に関する設定」を行います。
- 下部全体(Arpeggiator, MIDI / Wheel & プリセット管理):
- 中央下部にあるのがArpeggiator(アルペジエーター) セクション。和音を自動で分散演奏してくれる機能です。
- その右隣にMIDI / Wheel(MIDI/ホイール) セクション。MIDIコントローラー(モジュレーションホイールなど)の動作を設定します。
- 最下部にあるのがプリセット表示と管理のエリア。音色を呼び出したり、自分で作った音色を保存したりする場所です。
これらのセクションが、Synth1のシンプルなパネル上に効率的に配置されていることを、ぜひ実際のUI画像で確認してみてください。
Synth1での音作りの「流れ」を追う:信号の旅路を理解する
シンセサイザーの音作りは、まるで「音」という材料を使って料理をするようなものです。まずは材料(波形)を作り、次にその材料を加工し(フィルター)、時間ごとの変化を決め(アンプ)、さらに味付け(モジュレーションやエフェクト)をしていく、というイメージです。
Synth1のUIは、この音の信号が流れる順序に非常に忠実に設計されています。この流れを理解することが、パラメーターがなぜそこに配置されているのか、そして何を調整すれば、音のどの部分に影響が出るのかを把握する上で非常に重要です。
音作りの基本フローとSynth1 UIの対応

MIDIキーボードやDAWのピアノロールでノートを打ち込むと、その信号がSynth1に入力され、以下のような経路で音が生成され、変化していきます。
MIDI入力(DAW/MIDIキーボードからの演奏情報)
↓
[ Oscillators部 (音の元となる波形を生成) ] ← UI左側の「Oscillators」セクション
↑ ← (この部分に「Modulation」が影響を与えることがある)
↓
[ Filter部 (音の周波数特性を変化させ音色を加工) ] ← UI中央上部の「Filter」セuxション
↑ ← (この部分に「Modulation」が影響を与えることがある)
↓
[ Amplifier部 (音量変化を制御) ] ← UI中央上部の「Amplifier」セクション
↑ ← (この部分に「Modulation」が影響を与えることがある)
↓
[ Effect部 (空間系・変調系効果を付加) ] ← UI右側の「Effect」セクション
↓
最終的なサウンド出力
- MIDI入力: あなたが演奏したMIDIデータは、まずSynth1に送られます。この情報は、音の高さ(どの鍵盤が押されたか)、音の強さ(ベロシティ)、そしてMIDIコントローラー(モジュレーションホイールなど)の動きとしてSynth1に伝わります。
- Oscillators部(音の源泉): UIの左側「Oscillators」セクション。ここで、音の基本的な「声」となる波形(ノコギリ波、矩形波など)が生成されます。複数のオシレーターを組み合わせたり、デチューンをかけたりすることで、ここで既に音の厚みや複雑さが決まります。
- Filter部(音色の形成): 生成された波形は、次にUIの中央上部「Filter」セクションへと送られます。ここでは、特定の周波数帯を「削ったり」「強調したり」することで、音色に様々な「形」を与えます。例えば、高音域をカットして柔らかなパッドにしたり、レゾナンスを上げて鋭いリードサウンドにしたりします。
- Amplifier部(音量の調整と時間変化): フィルターを通過した音は、UIの中央上部「Amplifier」セクションへと進みます。ここでは、音の全体的な音量を調整するだけでなく、ADSRエンベロープを使って、音が「どのように立ち上がり、どのように減衰し、どのくらい持続し、どのように消えていくか」という時間的な変化を決定します。
- Modulation(音に動きを与える): UIの「LFO」セクションや、各セクションのエンベロープ(A/D/S/R) は、直接音が流れる経路ではありませんが、オシレーターのピッチ、フィルターのカットオフ、アンプの音量など、さまざまなパラメーターに対して「時間的な変化」や「周期的な揺らぎ」を与えます。これにより、音色に生き生きとした「動き」や「表情」が生まれます。
- Effect部(最終的な彩り): アンプを通過した音は、最後にUIの右側「Effect」セクションへと送られます。ここで、ディレイ(やまびこ効果)やコーラス/フランジャー(音の厚みや広がり)といったエフェクトが適用され、サウンドに空間的な「彩り」と「奥行き」が加わります。
- Global部(全体設定): フロー図には直接表れませんが、UI右下の「Voice」セクションや、下部の「Arpeggiator」セクション、「MIDI / Wheel」セクションは、シンセ全体の同時発音数、ポルタメント(音の繋がり)、アルペジオのパターン、MIDIコントローラーの動作など、演奏全体の「振る舞い」を設定する重要な役割を担っています。
この信号の流れを理解することは、あなたが狙った音色を作り出す上で非常に強力なヒントになります。
次回の記事では、「各セクション・パラメーター詳細解説」として、それぞれのセクションにある具体的なノブやボタンが、この音作りのフローのどの部分に影響を与え、どのような音の変化をもたらすのかを、UI画像と照らし合わせながらさらに深く掘り下げていきます。お楽しみに!

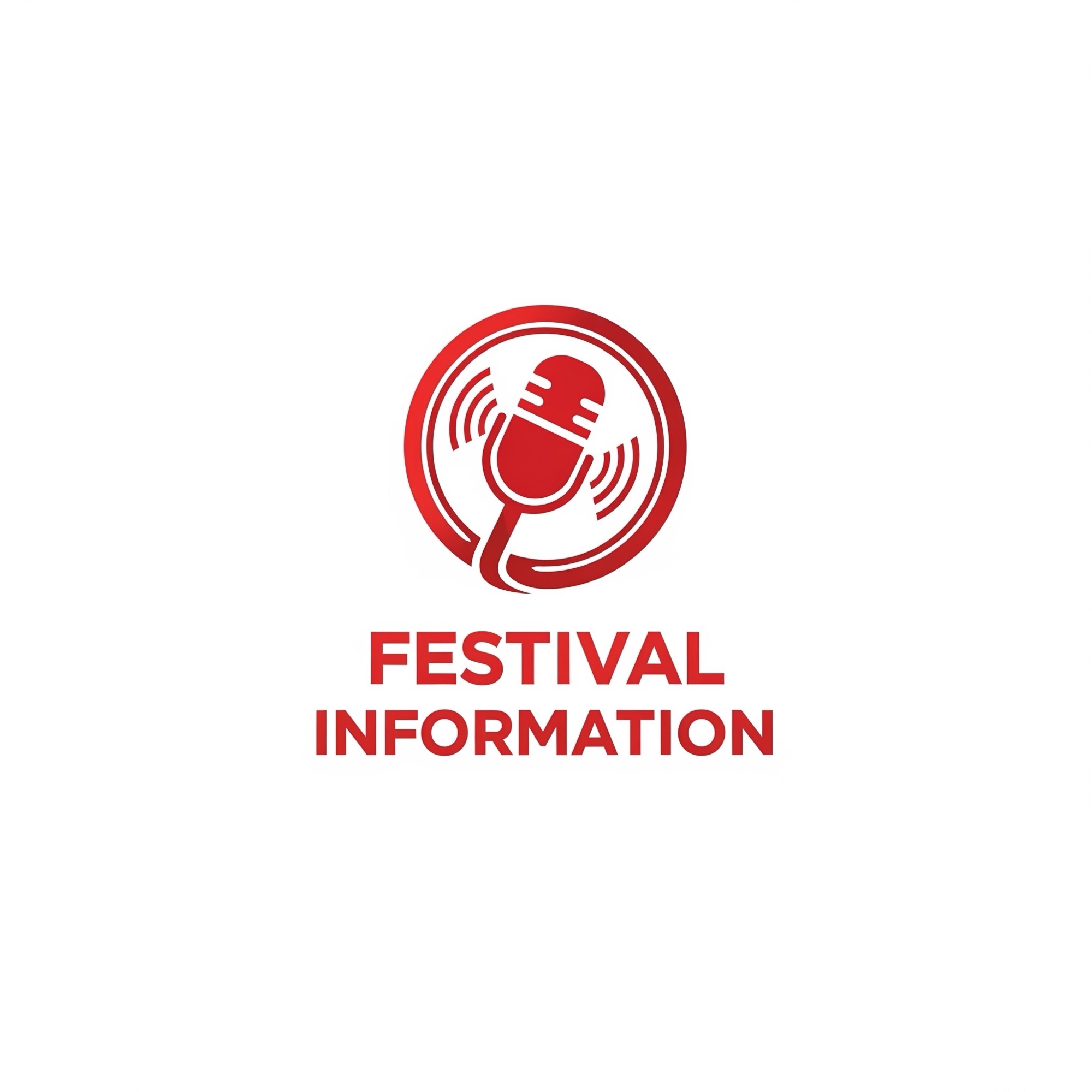
No responses yet